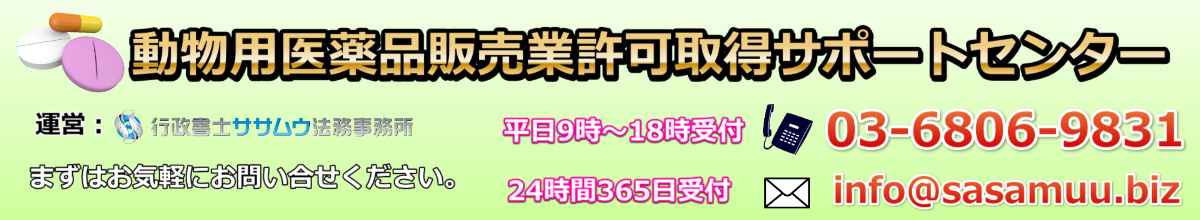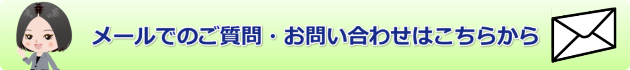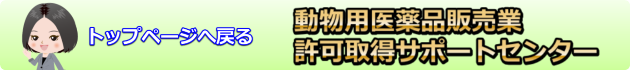平成26年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品医療機器等法」といいます)が施行されました。これは、従来の「薬事法」の内容の一部が改正され、名称も改変されたものですが、保健衛生上極めて重要な医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」といいます)について、その運用等を定めたものであることに変わりはありません。
医薬品等は人用のものを指します。一方、専ら動物に使用する医薬品等を「動物用医薬品等」と言い、人用の医薬品と同様に医薬品医療機器等法によって、その運用等が規制されています。
もっとも、動物であればどのような動物でも動物用医薬品等の対象となるものではなく、以下のような動物がその対象とされています。
- 産業動物
- 伴侶動物
家畜:牛、豚、めん羊、山羊、馬
家きん:鶏、あひる、うずら、七面鳥
魚:養殖水産動物
 その他:みつばち、蚕、ミンク
その他:みつばち、蚕、ミンク
犬、猫、小鳥、鑑賞魚
人用医薬品との違い
人用医薬品と動物用医薬品との違いを理解するため、あなたが風邪をひいた場合を例に考えてみましょう。
風邪をひいた場合、特に何の対処もすることなく治してしまうという方もいらっしゃるとは思いますが、多くの場合、薬局やドラッグストアで風邪薬を購入したり、病院に行って診察を受けて薬の処方を受けるかと思います。薬局やドラッグストアで購入する風邪薬はいわゆる大衆薬(一般用医薬品(OTC医薬品))と呼ばれ、処方箋による薬は医療用医薬品(処方薬)と呼ばれます。
では、今度はあなたではなく、あなたの大切な家族の一員とも言える犬や猫等の小動物が病気になった場合を考えてみましょう。
この場合、基本的には動物病院に連れて行って獣医師に診てもらうと思います。一部の動物用医薬品は量販店やドラッグストアでの購入も可能ですが、小動物を対象とした医薬品の多くは動物病院での処方となります。また、産業動物(主に食用となる家畜や養殖水産動物)と対象とする動物用医薬品の場合も、診察した獣医師(水産用ワクチンの場合は、水産試験場の技術者)の処方となります。
処方薬とそうでない薬があることや、効果と安全性が証明されないものは薬として認められないという点においては人用医薬品と動物用医薬品に違いはありません。
ですが、特に産業動物に対する動物用医薬品の使用方法においては大きな違いがあります。それは、その薬を使った動物に由来する食品(肉、卵、乳及び水産物等)に、その薬が残らないような使い方が法律で決められ、治療効果だけでなく食品としての安全性が守られなければならないという点です。
▼まずは、こちらからお問い合わせください。